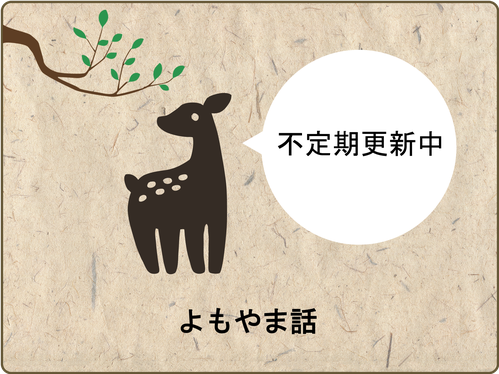よもやま話を更新しました。
もう駄目です、春が始まってしまったので
意識が内から外へ移ってしまいました。
自分の内面を写すよもやま話、
グリーンシーズンは滞りそうです。
そんな私の言い分、聞いてください。
→毎日変化する春の森はソワソワする。
PM2.5で霞む空と太平洋
昨日のPM2.5は濃かったですね。
霧が出て海が見えない、
というのはここでは
珍しくありませんが、
PM2.5で海が霞むって結構ヒドイ。

そんな昨日よりマシですが、
今日もPM2.5の影響で
晴れているのに
どんよりした景色です。

なるべくなら外の空気を吸わない方が
良いのでしょうが、そうは言っても
動植物の活動が賑やかになってきているので
森の様子が気になって仕方がありません。
カラスやカササギがせっせと枝を運び、
カラ類はあちこちでさえずり、
足元の植物は日ごとに緑を濃くし、
最近ではカワラヒワが元気よくさえずり始めました。
ちょっとソワソワしますね。
室蘭では春が進行中

待ったなしの季節がやってきました。
眠ったように静かだった森の中は、
どんどん動き出しています。
エゾエンゴサクはまもなく開花するでしょう。

キクザキイチゲはまもなく見頃を迎え、

エゾアカガエルもそろそろ合唱&産卵です。

エゾサンショウウオの産卵も始まってます。

夏鳥も渡ってくる頃でしょう。
今日は何も確認できませんでしたが、
キレンジャク(若)の羽を拾いました。

状態非常に良く、初列・次列風切羽に
関しては全部回収できたかも。
これから整理しようと思います。
詳細はまた後日に。
さ、フィールドに動植物整理に、
忙しくなります。
早春に入った室蘭

本州では桜の季節を迎えようとしていますが、
室蘭はようやく平地での雪解けが進み、
早春を迎えています。
これでも、北海道の他の地域に比べれば
ダントツで季節の進行が早い場所です。
水辺ではミズバショウがあと数日で
開花しそうな勢いです。

ナニワズも同上。

チシマネコノメソウも同上。 笑

フッキソウが
シカに食べられていました。
シカは食べないと言われる植物ですが、
食べ物に困ると口にすることはあるようです。
洞爺湖の中島に生息するシカのように。
でも、ここは積雪の低い地域。
冬でもササはいくらでもあったのに。
あれですかね、雪に被っていない分
枯れかかった葉ばかりで嫌だったんでしょうか。
去年はオオハンゴンソウも食べてたし。
この辺りのシカたちは、
ちょっとずつ、食性が変化しているのかも?
なぜ現代人には虫嫌いが多いのか? -を検証した発表が興味深い
現代人には虫嫌いな人が多いのは、
虫に触れる機会が減った、とか
虫に対する知識が足りないから、とか
いろいろと言われていますが、
それを検証した人が現れました。
東京大学の深野祐也氏と曽我昌史氏は、
進化心理学的観点から13,000人に対して
調査しています。すごいですね。
ところで、進化心理学という学問、
初めて耳にしました。
ウィキペディアによると、
「進化心理学(しんかしんりがく、英語:evolutionary psychology)とはヒトの心理メカニズムの多くは進化生物学の意味で生物学的適応であると仮定しヒトの心理を研究するアプローチのこと。」
らしいです。

いわゆる「虫」たちは生態系の中で、
花粉媒介者、他の生き物の餌、分解者、
など重要な役割を担っています。
そして、地球上の生物170万種のうち、
虫は95万種以上と圧倒的繁栄を
遂げている生き物です。
植 物(約27万種)
哺乳類(約6,000種)
鳥 類(約9,000種)
魚 類(2万5千~3万種)
そして、そして、
世界中の虫たちの40%は減少傾向にあり、
数十年で絶滅する可能性があるという
論文が出るほど、
虫を取り巻く状況は悪化しています。
保全に対する熱量が上がらないのはなぜか。
ここで示されている
虫嫌いというのがキーワードになりそうです。
→なぜ現代人には虫嫌いが多いのか?ー進化心理学に基づいた新仮設の提案と検証ー
春の渡り

本州で越冬していた鳥たちは、
北の繁殖地に向けて移動する
季節になっています。
マガンも然り。
一時滞在中は落穂探しに夢中です。

同じ水田地帯ではカラスの集団も。
おっミヤマガラスも来てるかな~
と双眼鏡覗くとハシボソガラスでした。
遠目&パッと見た時の姿が似てるんです。

近くにいた別のカラス集団は、
ミヤマガラスと判明。

尾羽根を扇のように広げて
頭を突き出して鳴く動きは
特徴的ですね。

港へ行くと、
スズガモ、カルガモ、コガモ、キンクロハジロ、
ヒドリガモ、マガモ、ホオジロガモ、ウミアイサが
いつも以上に集結していました。
渡りの途中かもしれませんね。
そんな中、コガモたちは求愛に忙しそう。
頭が茶色で目の周りが緑色のオスが2羽、
メス(全身地味色)の周りで求愛しています。
がんばれよー。
近づく春の気配はフクジュソウとアトリから

もともと積雪の低い室蘭は、
太陽が出て気温が上がると
一気に地面が広がります。
それと共に、
小さな虫が飛ぶようになり
フクジュソウも開花します。
冬が明け春が来ようとしています。

スーパーで買い物を終えて
運転席に乗り込むと、
駐車場の片隅に小鳥の小群が
いるのに気が付きました。
やけに辺りを警戒して地面に降りるので
なんぞや?と見るとアトリでした。
アトリという鳥は、
本州では冬鳥、
北海道では旅鳥
(一部は越冬、室蘭でも厳冬期に見てます)。
繁殖はユーラシア大陸の亜寒帯なので、
ここにいるのは一時的なもの。
基本的には、春と秋に見る機会が
増える鳥なのでフクジュソウ同様、
これを見ると季節の移ろいを感じます。

繁殖地へ向けて移動する前に、
まぐれでさえずったりしないか?
とちょっと様子を見てみましたが、
それは流石にまだ早いですよね。
今は食事優先です。
苫小牧市にある錦大沼公園
苫小牧市にある錦大沼公園、
室蘭市からは車で約1時間。
しょっちゅうは行かないけど
たまには行く公園です。

気温は-1℃ほど。
肌寒くはありますが、
日差しからは春がそこまで
来ているのだと感じられます。

今日は小沼一周。
(錦大沼公園に来て本丸に行かない私たち 笑)
冬が後退し始め、
徐々に解けているとはいえ
まだ結氷エリアは多く、
水鳥はほぼ皆無。
唯一いたぞ、と見ている先には

チュウダイサギでした。
相変わらず白が眩しいね。
ワカサギでも食べてるんでしょうか。

急にしゃがみ込んで
観察始めるので、
油断すると彼方へ
置いてけぼりになります。

何見てたのって
アライグマの足跡です。
アライグマは普通に歩いていると
右前足の左横に左後足
左前足の右横に右後足
というように、対になって付きます。
後足はかかとまでべったり着地するので、
前足より長い足跡になります。

そう言えば、地球岬の散策路にある
池の氷もそろそろ解け始める頃でしょうか。
あちらのアライグマの動きも気になります。
近い内にまた見に行こう。
閲覧注意、セッケイカワゲラとダニとおぼしき生き物

3/2に大量に降った湿った雪は
太陽に照らされてどんどん
解け始めています。
森に入ると梢に積もった雪が
「暑い暑い。」と言って(いるような気がする)
パラパラ音を立てて落ちていきます。
時々、私の頭上にも雪玉が「イエーイ!」と
(言ってないけど)落下してきます。

そうしていつものように、
雪と戯れながらセッケイカワゲラと
言われているクロカワゲラ科の
仲間たちを見ていると、
黒い体に赤い点々が見られました。
以下、昆虫のアップ写真が続きます。
虫が平気な人でも苦手に感じる
かもしれませんのでご注意ください。

このような赤い点、
はて何でしょう。

付着している場所や数は
一定していません。

こちらのは、赤いものが
複数まとまってちょっと気持ち悪い。
何かめくれてるし。

有翅タイプにもありましたね。
うっすら赤いのが透けて見えてます。

セッケイカワゲラは7mmほど。
その体につく赤いものは
1mmに満たないのでこれ以上
大きく撮影するのは困難です。
動くし撮影機材の限界です^^
捕らえて亡き者にしたのち
ルーペでじっくり見るなり
マクロ撮影するなりすれば
この赤いものが何者かはっきり
するのでしょうけど、そこまでは、ね。

そして、何十匹と追いかけ回して
いる内にこれが撮れました。
ダニの仲間のようです。
今まさに本体に取り付く所?
このダニの目的はなんでしょう。
ただの便乗ではないような、
体液でも吸うんでしょうか。
ニセコにいた時もセッケイカワゲラは
頻繁に目にしてましたが、
こんなの付いてたかなぁ。
気がついてなかっただけでしょうか。

ちなみにこの場所の
セッケイカワゲラ、
ダニが付いてないのを
探すほうが大変なほどの
付着率でした。
あくまで、私がざっと見て回った
限りの話ですが。
一度気がつくと興味が湧くもので
他のエリアのセッケイカワゲラにも
このダニが付いているのかどうか
気になってきました^^
雪がある内に見ておこうかな。
室蘭は春が近づいてきました

室蘭では、春の日差しが
感じられるように
なってきました。
山の中はこんな景色ですが、
あと10日ほどしたら
ふもとではフクジュソウが
ちらほらと咲き始めることでしょう。

この時期は、
暖かく風穏やかな日に
セッケイカワゲラ
(クロカワゲラ科の一種)が
繁殖のために上流へ向けて
歩いている所に出くわします。
とても小さな虫なので
いつもこんな風に撮ってます。
撮った画像はInstagramにて公開中です^^